相続登記の義務化

改正法の成立
所有者不明土地が社会問題となっています。浜松でも、駅に近い中区などにおいても、誰も住んでいない住居等が散見されるようになってきました。
そうした問題の解決に向けて、先の令和3年4月21日、参議院本会議で民法・不動産登記法等が改正されることとなりました。今回の改正においての目玉は「相続登記の義務化」です。「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(総称して以下「改正法等」)が成立し、それに伴い、不動産登記法も改正されます。
改正法等は、令和3年4月28日から2年以内に施行され、不動産登記法は、3年以内に改正される予定です。なお、これまで同様に義務ではなかった「住所変更登記」についても、5年以内に改正されることとなっています。
これまで、相続登記は、義務ではなく、例えば亡くなられた後10年後に登記を行うことも可能でした。実際に実務においてもこうした事例は少なくありません。しかし、この改正法等が施行されて以降は、相続登記が義務化されることとなります。ここで概要を見てみましょう。
相続登記関係の改正
改正不動産登記法においては、以下の条文が新設されます。要約して紹介します。
改正不動産登記法第76条の二 要約
第76条の二(相続登記による所有権移転登記)
相続により所有権を取得した者は、相続の開始のあったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならない。遺贈により所有権を取得した者(但し相続人に対する遺贈に限る)も同様とする。
2 法定相続分で相続登記をし、その後に遺産分割によって当該相続分を超えて相続分を取得した者は、当該分割協議の日から3年以内に登記をしなければならない。
法律というのは、いつも、あえて分かりにく表現で記載されますが、この条文もなかなか判断に迷う部分があります。
3年以内に登記しなければならない者とは
以下の要件を全て満たす者
- 相続の開始を知った者
- 不動産の所有権を取得したことを知った者
これを解釈すると、被相続人が亡くなったことを知らない相続人は、当然に登記の義務は発生しないので言うまでもありませんが、亡くなったことを知った相続人であっても、遺産分割未了で確定的に不動産の取得をしていないのであれば、登記の義務が発生しないようにも読めます。
実務における相続登記では、①法定相続分に基づき登記する場合(遺産分割協議未了)と②遺産分割協議に基づき登記する場合がありますが、多くの事例において後者の遺産分割協議書に基づき申請されます。相続が開始されると、相続財産は、遺産共有状態となり、法定相続分に基づいた持分で共有されます。遺産分割をすると、その共有状態を解消し、特定の取得者(単独あるいは共有)にある遺産を確定的に取得させることができるのです。
改正不動産登記法第76条の二第2項は、一旦法定相続分で登記をし、その後に遺産分割協議を行い、当該相続分を超えて不動産を取得した者は登記をしなければならないという規定です。つまり、先の①を申請した場合に該当します。前述のとおり、実務では、ほぼ遺産分割協議に基づき登記が行われます。法定相続分で登記をしても、それは遺産共有状態を公示しているにすぎず、後日あらためて遺産分割協議を行う必要が生じる場合も想定され得ること(その場合2度手間になります)、また仮に相続人全員の合意ができない場合に、法定相続分で登記をしても、あくまでも共有状態を公示しているに過ぎませんので、将来的な不動産の処分等において(売買などの処分行為には共有者全員の同意が必要)、共有状態であるゆえの問題が生じる可能性もあります。こうしたことから、法定相続分で登記することは、現状あまり多くありません。仮に相続登記義務化以降、とりあえず法定相続分で登記したとしても、結局そのあと遺産分割協議を行うのであれば、またそこから3年以内の登記義務が発生することや後述の申し出制度を考慮すると、このような手続きを取ることは多くないことが想定され、結果、76条の二第2項については、それほど影響はないかもしれません。
いずれにしても、今回民法においても、10年経過後の遺産分割協議においては、特別受益、寄与分の利益が考慮されなくなる規定が新設されることを考慮しても、仮に76条の二第1項でいう、「不動産を取得した者」に、遺産分割未了の相続人が含まれないのであれば、遺産分割協議を死亡から数年後に行う方も多い現状を鑑みると、この改正法等により相続登記の申請を促進させる意義も薄れてしまうため、この「不動産を取得した者」には、遺産共有状態の相続人も含まれると考えるのが妥当かもしれません。
追記10月1日 この点につき遺産共有状態の相続人にも登記義務があることが、法務省資料により明確となりました。別ブログにて説明しています。
また、改正不動産登記法においては、次の条文も新設されます。同じく要約して紹介します。
改正不動産登記法第76条の三 要約
第76条の三(相続人による申し出)
不動産の所有権を取得した者は、登記官に自らが登記名義人(被相続人)の相続人である旨を申し出ることができる。
2 申し出をすると、76条の二第1項の登記義務(当該申し出の前の遺産分割によるものを除く)を履行したものとみなされる。
3 申し出があったときは、登記官は職権で申し出者の住所氏名を登記できる。
4 申し出をした者は、申し出をした後に、遺産分割協議をしたときは、遺産分割協議の日から3年以内に登記を申請しなければならない。
以下略
先ほどの「不動産を取得した者」の定義の話に戻りますが、76条の三第2項及び第4項の規定を考慮すると、やはり、遺産分割未了の相続人にも登記の申請義務があるということなのでしょうか。であるからこそ、第2項において、(当該申し出前の遺産分割によるものを除く)と記載され、第4項遺産分割前においても申し出をする前提でこの規定が置かれている訳です。
先ほど述べたように、実務では、遺産分割未了の法定相続分で登記することは、多くありません。第76条の三第1項、第2項は、そうした実務、実情を反映した規定ととることができます。
本来、相続登記を申請しなければ過料に処されるところ、登記ではなく、申し出をすれば、その義務が免除されます。登記官は、その申し出にしたがって、登記記録に、住所氏名などを付記して記録することとなります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。スムーズにまとまる場合もあれば、ちょっとした食い違いから合意に至るまで長期に及ぶ場合、そもそも協議自体を拒む相続人などが存在する場合もあります。また、相続人のうち判断能力に欠ける方がいる場合には、遺産分割協議の前提として成年後見人等の選任手続が必要となる場合もあります。
こうしたことから、亡くなられた日から3年で協議がまとまらない場合も十分考えられるため、このような規定が置かれることとなったのでしょう。
改正不動産登記法第76条の四 要約
第76条の四(所有権登記名義人についての符号の表示)
登記官は、所有権登記名義人が権利能力を有しなくなった場合(法務省令で定める場合に限る)は、法務省令で定めるところにより職権でその旨を記録できる。
権利能力を有しなくなった場合とは、つまり死亡した場合のことです。
民法第3条第1項「私権の享有は出生に始まる」。
この規定により、仮に相続人の方が相続登記や申し出を怠った場合であっても、登記官が、行政間(住基ネット等)でその情報を取得し、その死亡の情報を登記できるようになります。よって、その登記記録を見た人は、その所有権登記名義人が亡くなっていることを知ることができます。
改正不動産登記法第119条の二 要約
第119条の二(所有不動産記録証明書)
何人も、手数料を納付して、自らが所有権登記名義人として記録されていることを証明した書類の交付を登記官に請求できる。
2 所有権登記名義人の相続人等は、前項の証明書類の交付を請求できる。
実務上、相続財産として不動産を検索するために、市町村町における名寄せ帳や固定資産評価証明書を取得することがあります。しかし、これらはあくまでも特定の市町村町毎における不動産を確認できるだけであり、他の市町村町における不動産は、別途、その市町村町に書類を請求しなければなりません。現実的には、固定資産税納付書が毎年送付されてきますので、相続財産中の不動産を見落とす可能性はあまりありませんが、共有持分の不動産などは、そのうちの1名にのみ固定資産税納付書が発送されることを鑑みると、有用となる面もあるかもしれません。
改正不動産登記法第164条第1項 要約
第164条第1項(過料)
第76条の二及び第76条の三第4項の規定に基づく申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処する。
過料に関する規定です。第76条の二(登記義務)及び第76条の三第4項(申し出後の遺産分割協議による登記義務)を怠った場合は、最高10万円の過料に処せられます。
住所変更登記の改正
今回の改正で、住所変更登記も義務化されることとなりました。
改正不動産登記法第76条の五 要約
第76条の五(所有権登記名義人氏名変更等)
所有権の登記名義人の住所氏名に変更があった場合は、2年以内に登記をしなければならない
そもそも不動産登記における権利部の登記は義務ではありません。前項で述べた相続登記の義務化は、相続登記の未申請により所有者不明土地がネズミ算的に増加していくことを防止する施策です。この住所氏名変更登記も、いわば同じ意図から、改正により義務化されることとなりました。もちろん法人も対象です。
改正不動産登記法第76条の六 要約
第76条の六(職権による氏名変更登記)
登記官は、法務省令で定めるところにより、所有権登記名義人の住所氏名に変更があった場合には、職権で登記することができる。但し、自然人の場合は、申し出があった場合に限る。
第76条の五を補完する条文です。行政間で連絡を取り、住所氏名変更登記をしない場合に、職権で登記できる規定です。ただし、個人は申し出があった場合のみと規定されています。
改正不動産登記法第164条第2項 要約
第164条第2項(過料)
第76条の五の規定に基づく申請を怠った場合は、5万円以下の過料に処する。
住所氏名変更登記についても、申請を怠った場合には、過料が課されます。
その他不動産登記法改正
上記、相続登記、住所氏名変更以外では、以下の登記が改正されます。
改正不動産登記法第63条第3項 要約
第63条第3項
遺贈による所有権移転登記(相続人に対する遺贈に限る)は、登記権利者が単独で申請できる。
これまで遺贈を原因とした登記は、共同申請により登記しなければなりませんでしたが、受遺者が相続人であれば単独で申請できるようになります。
改正不動産登記法第69条の二 要約
第69条の二(買戻特約の抹消)
買戻し特約の登記がされている場合において、契約日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で買戻権抹消の申請できる。
同様に、これまで共同申請で行っていた買戻権抹消の登記を単独で申請できるようになります。といっても、多くは、土地開発公社、住宅公社などが買戻権を付けることが多く、その場合の抹消登記は、嘱託登記となり、現状も実質的に単独申請に類するものです。
改正不動産登記法第70条の二 要約
第70条の二(解散した法人の担保権抹消)
担保権者である法人が解散し、法務省令で定める方法で調査してもなおその法人の清算人の所在が知れないときは、弁済期から30年、かつ、解散から30年経過しているときは、登記権利者は単独で担保権の抹消ができる。
実務において、古い解散した法人の抵当権が登記記録に残っているときがあります。その場合、その法人の清算人を探し出し、その清算人と一緒に、抵当権を共同で抹消しなければならず、手間がかかったところ、法務省令で定める方法で調査しても、清算人がどこにいるか不明な場合は、弁済期及び解散日から30年経過していれば、登記権利者が単独で抹消登記を申請できる規定が新設されます。
改正不動産登記法第73条の二 要約
第73条の二(所有権の登記事項)
1 法人の場合は会社法人等番号
2 所有権登記名義人が国内に居住していないときは、その国内における連絡先となる者の氏名住所等
この規定も、所有者不明土地の問題から新設される規定です。会社法人等番号を記載することにより、後日、その会社を調査する際の手間が軽減されます。また、国外在住の名義人の住所氏名はこれまでとおり登記されますが、それに加えて国内の連絡先も登記されることとなりました。
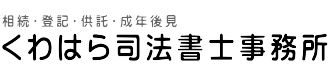
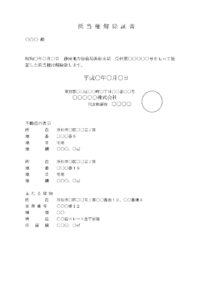

“相続登記の義務化” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。